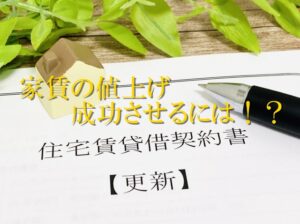マンションをはじめとする不動産を賃貸に出す場合は、入居者を募集して終わりではなく、入居中の管理も必要となります。賃貸管理業務はオーナー自ら対応することも可能ですが、現実的には不動産会社に委託することになるでしょう。
その際の賃貸管理手数料は、毎月の家賃の3%〜10%程度の範囲が相場ですが、手数料率が5%を超えてくると負担に感じる方もいるかもしれません。この記事では賃貸管理手数料に含まれる業務内容を紹介しつつ、手数料率が5%を超える管理会社は高いのか判断するためのポイントを解説します。
賃貸管理手数料とは?
そもそも不動産管理とは、賃貸物件の状態を良好に維持管理するための業務はもちろん、家賃回収や督促、さらには入居者からのクレーム対応など、賃貸経営に関わるさまざまな業務を指します。これら賃貸経営にまつわる業務をアウトソースするための費用が、賃貸管理手数料です。
マンションでは、賃貸管理手数料と似た名称の「共益費」「修繕積立金」などを徴収されることもあるでしょう。共益費については、マンション共用部を維持管理するための費用です。厳密には別のコストですが、同じ意味として使われることもあります。
一方、修繕積立金は分譲マンションで10〜15年ごとに行われる「大規模修繕」に備えるための費用です。賃貸管理手数料は不動産会社へ支払いますが、修繕積立金は管理組合に支払います。双方とも毎月かかるランニングコストですが、目的が異なることは覚えておきましょう。

賃貸管理手数料の相場
賃貸管理手数料率の相場は3%〜10%ですが、どの範囲の業務まで任せるのかによって異なります。委託パターンごとに、管理委託手数料の相場をみていきましょう。
一般的な管理手数料は家賃の5%程度
物件管理や入居者管理など賃貸管理業務全般を委託するケースでは、家賃の5%程度が相場です。管理手数料の計算における家賃には、物件賃料以外の共益費や管理費なども含みます。空室の場合は、その部屋に対する賃貸管理手数料は基本的にはかかりません。しかし、物件一棟の管理業務を丸ごと委託する場合などは、空室有無に関わらずに管理手数料が計算されることもあるため、契約内容はよく確認しておきましょう。
集金管理のみ委託の場合は3%程度
集金管理のみを委託する場合は、家賃の3%程度が相場です。集金管理には毎月の家賃回収はもちろん、滞納時の督促も含まれます。賃貸経営において心理的にも負担となりやすい業務が家賃回収です。必ずしもスムーズに支払ってくれる借主ばかりではないため、金銭に関わる交渉のみは不動産管理会社に委託してもいいでしょう。
サブリースの管理手数料の相場は10~20%程度
管理会社が物件を一括で借り上げ、エンドユーザーへ転貸するモデルは「サブリース」と呼ばれます。サブリースの場合は、オーナーから見たときの借主は管理会社であるため、たとえ入居者がいなくても管理会社から賃料が支払われることが特徴です。
空室リスクがないことはメリットですが、その反面として管理手数料が高く、家賃の10〜20%程度が相場です。サブリース契約で利益が出るかどうかは物件ごとの状況によっても異なるため、あらかじめ収支計算しておきましょう。
近年は、賃貸管理手数料を低めに設定している場合も多い
賃貸管理手数料率の相場は平均すると家賃収入の5%程度ですが、近年は管理手数料を1〜3%と低めに設定している管理会社も存在します。また、家賃収入に対する両立ではなく、1戸あたりの管理料を定額で定めている管理会社もいます。
都心部の物件・築浅物件など入居需要が高い物件では、管理手数料が低めに設定されていることも多いため、複数の管理会社に見積もりをとってみてもいいでしょう。ただし、後述もしますが、管理手数料の低さだけで委託会社を決めると思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあるため注意してください。
手数料の設定は業務内容によっても異なる
賃貸管理手数料の設定は、任せる業務内容によっても異なります。幅広く物件管理を任せている場合は5%でも妥当であり、物件管理は任せずに家賃集金だけを委託するなら3%が相場です。しかし、集金代行だけで管理手数料が5%以上に設定されている場合は、割高だと判断できます。
そもそも賃貸管理手数料は、宅地建物取引業法など不動産関連の法律において定めがなく、それぞれの管理会社が自由に設定できます。その対応範囲も管理会社によってさまざまであるため、物件オーナーが任せたいと考える業務を自由に委託でき、それに応じて管理委託料が変わることが特徴です。コストパフォーマンスを重視する場合は管理手数料の料率だけで判断するのではなく、料率と委託内容のバランスを考慮して判断しましょう。
賃貸管理手数料に含まれる業務内容
ここからは、賃貸管理手数料に含まれる業務内容について紹介します。管理業務は大別すると「入居者に関する業務」と「建物に関する業務」に分けられ、それぞれ任せられる業務内容は次のとおりです。
| 業務種類 | 詳細 |
| 入居者に関する業務 | 入居者の募集 賃貸借契約書の作成、締結 クレームやトラブルの対応 集金管理 滞納の催促 退去の立ち合い、敷金の精算 原状回復の工事見積もり |
| 建物に関する業務 | 巡回 内装工事費用 設備交換 建物の清掃、点検 |
これらの中には、不動産オーナー自らが対応することが現実的ではない業務も含まれます。実際の業務内容を紹介します。管理業務を委託するかどうかの判断材料にしてみてください。
入居者に関する業務内容
入居者に関する業務は多岐にわたり、募集から契約、入居中のトラブルから家賃回収まで対応しなければなりません。それぞれ賃貸経営のコア業務ですが、不動産オーナーが対応するには心理的・身体的負担が大きいことも事実です。以下で、各業務の内容を紹介します。少しでも負担・不安に感じる方は、プロの不動産会社に委託することを検討してみてください。
入居者の募集
空室物件がある場合は、入居者募集まで任せられます。管理業務にも対応している不動産会社は、特定エリアに精通している傾向が強いです。このような不動産会社は賃貸需要も把握しているため、比較的早期に入居者を見つけてくれるでしょう。
なお、借主との契約が成立した場合には「仲介手数料」が発生します。(契約業務委託手数料などの名目になっていることもあります)賃貸契約における仲介手数料は「家賃1か月分 + 消費税」が上限とされており、これ以上請求されることはありません。なお、この上限は貸主・借主の双方から受け取る仲介手数料を合わせた額です。
貸主・借主の双方へ0.5か月分ずつ請求することもありますが、実務的には借主が1か月分を負担するケースが多いでしょう。ただし貸主に対しては、入居者募集にかかった広告費用なども請求されます。
賃貸借契約書の作成、締結
賃貸借契約は一度締結して終了ではなく、定期的な更新も必要です。契約期間満了が近づいたタイミングで借主へ連絡する必要がありますが、所有物件が多いと契約管理も煩雑になってしまいます。賃貸管理を委託しておけば、賃貸借契約書の作成から締結まで対応してもらえます。なお、契約更新頻度は2年に一度が一般的です。
更新時の手数料については毎月の管理手数料とは別に、契約更新後の新賃料の0.5か月分〜1か月分と定められているケースもあります。賃貸管理会社のプランごとに異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
クレームやトラブルの対応
入居者からのクレームや、水周り設備などのトラブルにも対応してもらえます。これらのクレームやトラブルは、24時間365日いつ発生するか予測できません。そのため、不動産オーナーが自ら対応すると、精神的にも身体的にも休まらないでしょう。イレギュラーな対応については、すべて不動産管理会社に委託することをおすすめします。
集金管理
入居者からの家賃が毎月振り込まれているか確認する作業も、管理会社に任せられます。管理戸数が多いと集金管理の手間も増えるため、他の管理業務とあわせて委託するケースも多いです。
滞納の催促
賃貸管理でもっとも負荷のかかる業務が、家賃滞納者への催促です。家賃を支払ってもらえなければ、各種コストをオーナー自らが負担しなければなりません。そして、家賃を支払わない入居者はクセが強いことも多く、交渉に慣れていない方がやりとりすることは難しいでしょう。
オーナーとして直接的に催促すると、支払い免除や値下げを要求されるかもしれません。このような交渉は心理的ストレスも大きく、入居者とのトラブルに発展する可能性もあります。滞納時の催促まで任せられる賃貸管理契約を結んでいれば、オーナーとしては安心して賃貸経営に集中できることがメリットです。
なお、家賃の滞納など発生しないと考えている方もいるかもしれません。しかし2023年10月に公表された「賃貸住宅市場景況感調査『日管協短観』(2022年4月~2023年3月)」によると、月末での1か月滞納率は次のようになっています。
| エリア | 2021年度 | 2022年度 |
| 首都圏 | 0.5% | 0.4% |
| 関西圏 | 1.7% | 3.3% |
| その他 | 2.3% | 2.3% |
| 全国 | 0.9% | 0.8% |
エリアにより異なりますが、滞納は少なからず発生します。入居者の属性によっても滞納率は変化しますが、滞納時の対策についても考えておいたほうが安心でしょう。
退去の立会い、敷金の精算
入居者の退去時の立会い・原状回復に伴う敷金の清算も賃貸管理の一環として委託できます。敷金とは賃貸借契約に伴い、借主から貸主に対する債務の保証金として預ける金銭です。敷金から充当される項目としては、次の2つが挙げられます。
- 未払い家賃
- 原状回復費用
未払い家賃はその金額が明確に分かるため、支払い額を巡ったトラブルにはならないでしょう。しかし、原状回復費用はどの範囲までを借主が負担するかを巡って、往々にしてトラブルになりやすい費用です。
そもそも借主には、原則として「原状回復義務」が生じます。原状回復とは、物件を「本来あるべき状態に戻す」ことです。たとえば、入居中に扉を壊してしまった場合は借主の負担で修理しなければなりません。しかし、損傷箇所について指摘したところ「入居前から壊れていた」と主張される可能性もあります。このように退去時には損傷箇所を巡るトラブルになるケースもあるため、その交渉を含めて管理業者に委託したほうがオーナーとしての負担を軽減できるでしょう。
なお、賃貸借契約における原状回復義務は、あくまでも「本来あるべき状態に戻す」ことを指します。建物を「入居前の状態に戻す」ことではありません。普通に暮らしているだけでも建物は経年劣化によって傷ついていきます。たとえば、毎日開け閉めする扉であれば、軋みが生じることも自然です。このような通常の劣化については、貸主の負担で修繕しなければなりません。借主が負担する修繕は、次の要素に起因するものに限られます。
- 故意・過失による損耗・毀損
- 善管注意義務違反による損耗・毀損
- 通常の使用を超える使用による損耗・毀損
扉の不具合で考えると、通常の開け閉めによる軋みは貸主負担ですが、家具の出し入れなどで付けた擦り傷などは借主負担だといえるでしょう。なお、国土交通省によって「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が整備されたことから、原状回復義務に知識のある借主も増えています。より一層、原状回復を巡る交渉が発生することが予想されるため、管理会社に一任したほうが安心です。
原状回復の工事見積もり
原状回復費用が必要な場合も、そもそもどのような工事をすべきなのか、さらにはどのくらいの費用が必要なのか、賃貸経営に慣れていない方は検討がつかないかもしれません。不動産会社に管理業務を委託している場合は、原状回復の工事見積もりにも対応してもらえます。
建物に関する業務内容
建物に関する管理業務は、入退去に伴う業務はもちろん、入居中の維持管理も含まれます。定期的な確認もあり、必要に応じた修繕も必要となるため、やはり不動産オーナー自らの対応は難しいかもしれません。
DIYが得意で建物管理に自信がある方もいるかもしれませんが、入居者の満足度を保つためには不動産会社へ委託したほうがいいでしょう。それぞれの業務内容について詳しく解説します。
巡回
定期的な巡回によって、建物の異常を早期に発見してもらえます。入居者に異変がないかチェックするためにも、巡回業務を任せられる管理業者に委託したほうが安心です。
内装工事費用
簡単な内装工事は、賃貸管理手数料の範囲内で対応してもらえる可能性もあります。多少の傷程度であればすぐに直してもらえるため、物件の価値を保ちやすいことがポイントです。
設備交換
ゴムパッキンなど簡単な設備も、貸管理手数料の範囲内で交換してもらえることがあります。軽微な水漏れ修理なども任せられ、入居者の不満を溜めづらいことはメリットでしょう。
建物の清掃、点検
オプション費用が必要となる場合もありますが、建物の清掃・点検も委託できます。入居者の満足度を高め、長期間にわたって住み続けてもらうためには清掃業務は欠かせません。他の賃貸物件との差別化ポイントにもなるため、ぜひ清掃まで任せてみてください。
賃貸管理手数料に含まれない業務内容
さて、ここまで賃貸管理手数料に含まれる管理業務を多岐にわたり紹介してきましたが、次の費用は賃貸管理手数料には含まれません。
- 原状回復費用
- 室内設備の修理費
これらは別途予算を確保しておく必要があるため、あらかじめ想定しておきましょう。それぞれの業務内容とあわせて、予算相場も紹介します。
原状回復費用
貸主負担の原状回復費用そのものは、賃貸管理手数料では対応できません。経年劣化の程度によっても異なりますが、単身世帯向けの物件であれば修繕一回につき10〜15万円程度は想定しておいたほうがいいでしょう。ただし、賃貸管理会社のプランによっては、数万円までの原状回復費用が管理手数料内で保証されるケースもあります。
室内設備の修理費
エアコンやトイレ、キッチンなど室内設備の修繕費も、別途失費が必要です。水周り設備の修理には10万円以上の費用がかかることもあるため、万が一に備えて予算を確保しておきましょう。修理費についても賃貸管理会社のプランによっては、管理手数料内で一部を保証してくれます。
その他、会社によっても業務内容は異なる
ここまで各種管理業務を紹介してきましたが、実務的には管理会社ごとに任せられる業務内容はさまざまです。そもそも賃貸管理業務の依頼方法には次の2種類が存在します。
- 全部委託方式
- 一部委託方式
「全部委託方式」は、賃貸物件の管理業務全般を任せる方法です。すべて委託するためオーナー自身の負担は少なく、物件価値も保ちやすい方法といえます。一方で負担の大きい業務だけを管理業者に委託し、その他の管理業務はオーナー自らが手配する方法が「一部委託方式」です。
「一部委託方式」ではオーナーが自分で作業することもありますが、作業内容によってプロの業者へ依頼することもあります。管理手数料を抑えつつ、住民のニーズに合わせて物件管理できることがポイントです。その反面、オーナーの負担が大きくなりやすいことはデメリットだといえるでしょう。賃貸管理の委託範囲に決まりはないため、任せる業務については管理業者と相談してみてください。
賃貸管理手数料に関する注意点
賃貸管理手数料に関する注意点としては、下記の3つが挙げられます。
- 手数料の安さだけに注目しない
- 手数料に含まれる業務内容の幅を確認する
- 解約手数料の有無について確認する
委託会社とトラブルにならないように、契約前に確認しておきましょう。それぞれの注意点について詳しく解説します。
手数料の安さだけに注目しない
賃貸管理業者を選ぶ際は、手数料率の安さに注目してしまうかもしれません。しかし、管理手数料率の安さのみを理由に管理業者を決めてしまうと、肝心の管理業務品質が低い可能性もあります。管理業者のサービス品質は、そのまま入居者の暮らしやすさに直結します。
賃貸経営の実務を考えると、1%〜2%程度の管理手数料率の差よりも、入退去が繰り返されることによる空室リスクのほうが収益に影響することがポイントです。たとえば、1か月の賃料10万円のマンションを3室保有しているケースで考えてみましょう。3室とも貸し出している場合、合計賃料は30万円です。管理手数料率が3%の場合、毎月の管理手数料は9,000円であるため、手元に残る利益は29万1,000円となります。
しかし物件管理の質が悪く、1室退去された場合はどうなるでしょう。合計賃料は20万円・管理手数料は6,000円となるため、手元に残る利益は19万4,000円です。さらに入退去に伴って原状回復工事費用・入居者募集のための広告費用も発生します。管理手数料率の安さにつられて入居者の満足度をないがしろにすると、結果として利益が少なくなってしまう可能性があるのです。
もし管理手数料率5%の場合、合計賃料30万円のケースでは毎月の管理手数料は15,000円、手元に残る利益は28万5,000円となります。たしかに手数料率3%のケースと比べると2%利益率が下がりますが、入居者の不満が溜まり空室になることを考えると誤差の範囲内でしょう。
| 管理手数料率 | 入居戸数 | 合計家賃 | 管理手数料 | 利益 |
| 3% | 2戸 | 20万円 | 6,000円 | 19万4,000円 |
| 5% | 3戸 | 30万円 | 15,000円 | 28万5,000円 |
入居者の満足度が低く入退去が繰り返されると、その度に仲介手数料・原状回復工事費用を負担しなければならず、想定以上に資金繰りが厳しくなります。管理業者を選ぶときは手数料の安さだけではなく、サービス品質についても意識しましょう。
手数料に含まれる業務内容の幅を確認する
手数料に含まれる業務内容の幅を確認することも重要です。とくに管理手数料率が相場よりも低い場合は、諸々の管理業務がオプション扱いになっている可能性もあります。必要な業務を依頼した結果、最終的なコストは相場以上になってしまうかもしれません。
委託契約を結ぶ前に、毎月の賃貸管理手数料の中でどのくらいの業務を対応してもらえるのか確認してください。複数の管理業者を比べる際は手数料率のみならず、業務範囲も比べるようにしましょう。
また、先述した「原状回復費用の一部保証」のように、賃貸管理の一部として各種保証が用意されているケースも少なくありません。とくに注目しておきたい保証項目としては、次のような例が挙げられます。
- 滞納保証
- 死亡保証
- 早期解約違約金保証
- 更新料保証
家賃滞納時の督促だけではなく、滞納時の入金保証が付帯するサービスもあります。保証会社との契約が必要になる場合もありますが、家賃未回収のリスクを軽減できるためおすすめです。さらに入居者が死亡してしまった場合に、保証金がもらえるプランもあります。
孤独死や自殺によって事故物件となってしまうと、次の入居者がなかなか決まらない可能性が高いです。このようなリスクに備えるプランも、賃貸管理契約の一部として用意されているのです。
また、賃貸契約が早期に解約されてしまった場合の家賃保証や、入居者が更新料を支払えないときの入金保証など、賃貸経営に関係するあらゆるリスクに備える保証が付帯することも珍しくありません。手数料に含まれる業務内容とともに、保証されているリスクについても確認しておきましょう。
解約手数料の有無について確認する
物件管理を委託したものの、思うようなサービス品質ではない場合もあるでしょう。満足できない場合は解約することになりますが、解約手数料を請求されるケースも少なくありません。思いがけない費用を請求されないように、契約前に解約手数料の有無について確認しておきましょう。
優良な賃貸管理に委託する際のポイント
優良な賃貸管理に委託するためには、次のポイントを意識してみてください。
- 管理戸数はどのくらい請け負っているか
- 営業年数はどのくらいか
- 入居率は高いか
- コストや、賃料査定の根拠を開示してくれるか
- 手数料は複数の管理会社を比較する
それぞれの判断ポイントについて詳しく解説します。
管理戸数はどのくらい請け負っているか
管理戸数が多ければ多いほど、優良な賃貸管理業者だと思うかもしれません。しかし、管理業者のキャパシティを超えるほどの戸数を管理していると、きめ細かな対応が難しい可能性もあります。そのため、賃貸管理業者全体としてどのくらい管理戸数を請け負っているのか、さらに社員一人あたりがどのくらいの戸数を担当しているのかを確認してみてください。
たとえば、社員一人あたりの管理戸数が100戸〜150戸程度であれば、問題なく対応できる範囲だといえます。しかし、一人あたりの管理戸数が200戸を超えてくると、イレギュラーな業務への対応が難しくなってくるでしょう。
管理業者全体の管理戸数や従業員数は、それぞれの会社のホームページにも掲載されています。一人あたりの管理戸数は「全体の管理戸数÷従業員数」で概算できるため、参考までに計算してみてください。管理手数料率を見積もってもらう際に、担当者に直接尋ねてみてもいいでしょう。
営業年数はどのくらいか
賃貸管理業者としての営業年数も、優良な会社を見極める指標の一つです。長く営業している会社ほど、賃貸管理のスキルが高いことが予想されます。また、管理エリア独自の事情にも精通しているため、客付け力が高いことも期待できるでしょう。営業年数が数年に満たない管理会社は実務が未熟である可能性もあるため、注意してください。
なお、不動産会社(宅建業者)としての営業年数は、宅地建物取引業免許の更新回数から計算できます。宅建業の免許は、「都道府県知事(数字)免許番号」の順に記載されています。このカッコ内の数字が更新回数です。そして宅建業の免許は5年に一度更新されるため、開業5年未満の会社は(1)、開業6年目以降の会社は(2)、開業11年目以降は(3)と表記されることがポイントです。
入居率は高いか
管理物件の入居率についても要確認です。優良な賃貸管理業者が管理している物件は、入居率が高い傾向にあります。空室は賃貸収益に大きく影響するため、可能であれば入居率95%前後の賃貸管理会社を選ぶといいでしょう。(入居率の算出方法は管理会社ごと異なるため、1%程度の誤差を気にする必要はありません)
なお「賃貸住宅市場景況感調査『日管協短観』(2022年4月〜2023年3月)」によると、集金管理を含む委託管理物件の入居率は次のようになっています。
| エリア | 2021年度 | 2022年度 |
| 首都圏 | 94.6% | 94.4% |
| 関西圏 | 95.4% | 94.4% |
| その他 | 92.6% | 92.7% |
| 全国 | 93.6% | 94.0% |
このデータからも、入居率95%程度であれば問題のない範囲だといえるでしょう。なお、サブリースの場合は次のような入居率となっているため、一つの参考にしてみてください。
| エリア | 2021年度 | 2022年度 |
| 首都圏 | 98.9% | 97.3% |
| 関西圏 | 97.9% | 96.9% |
| その他 | 94.7% | 95.3% |
| 全国 | 98.7% | 97.3% |
コストや、賃料査定の根拠を開示してくれるか
賃貸管理業者と物件オーナーはビジネスパートナーであるため、信頼関係を築けるかどうかも判断ポイントになるでしょう。原状回復工事や内装工事のコスト、賃料査定の根拠を明示してくれる賃貸管理業者のほうが、安心して各種業務を任せられます。
手数料は複数の管理会社を比較する
賃貸管理業務の範囲が同じであっても、管理業者によって手数料率には差異があります。管理業務のクオリティが同じであれば、手数料率が低い管理会社に委託したい気持ちも自然なものです。
また、一社にしか見積もりを取っていないと、その手数料率が適正かどうかも分かりません。複数の管理会社を比較するためにも、2〜3社に見積もり依頼してみてください。
まとめ
賃貸管理手数料率の相場は3%〜10%と幅があり、任せる管理業務の範囲によって異なります。集金管理のみ委託する場合は3%程度、サブリース契約なら10〜20%程度となりますが、一般的な管理業務全般を委託する場合は家賃の5%程度が適正水準です。
管理業務のクオリティは、入居者の満足度に直結します。空室リスクを抑えるには、実績のある管理業者に委託したほうが安心です。株式会社クルーズカンパニーでは賃貸管理サービスも提供しており、借主へのサポートが充実していることが特徴です。賃貸管理にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
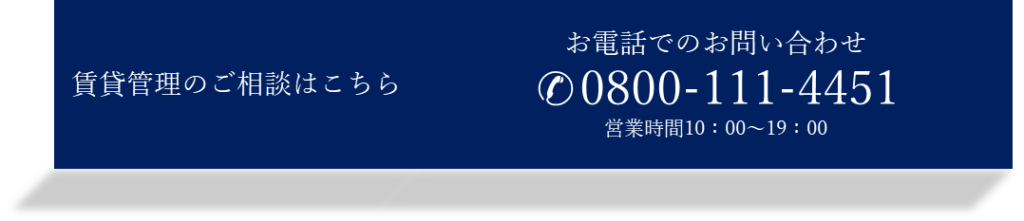
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 年末年始、夏季、GWを除いて無休 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-14-15 タウンウエストビル 7F |
| 電話番号 | 03-5909-4451 |
| アクセス | JR新宿駅西口・南口 徒歩5分 |